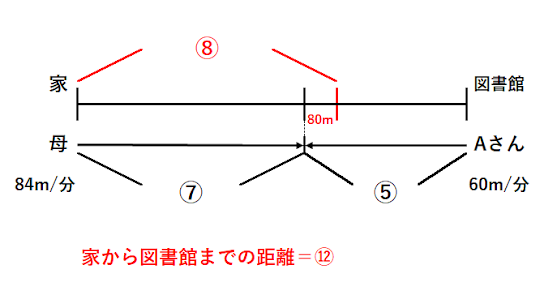【 問題 】3年生向け
10円玉と100円玉が合わせて50枚あります。なるべく多くの500円玉に両替したところ、100円玉はなくなり硬貨は全部で7枚になりました。100円玉は何枚ありましたか。
【 解答 】
つるかめ算の基本問題、3年生4年生でしっかり解いておきたいね。では、いきます。
100円玉がなくなったとあるから、10円玉と500円玉を合わせて7枚だね。順々に枚数をあてはめて確認してみる。
・500円玉=7枚、10円玉=0枚のとき
合計金額は500×7=3500円
10円と100円が50枚で3500円、つるかめ算で枚数を出しにいく。
10×50=500円
3500-500=3000円
3000÷(100-10)=✖・・・ 不適
50枚全部が10円だとすると10×50=500円、でも、実際は3500円だから3500-500=3000円高過ぎる、だから、100円と10円の差の90円で割ってあげると100円玉の枚数が出せるんだけど、3000÷90は整数値にならないから不適。7枚の内訳が500円玉7枚、10円玉0枚ではなかったということだね。
⇒( Read more » cf.つるかめ算2 )
・500円玉=6枚、10円玉=1枚のとき
合計金額は500×6+10×1=3010円
10円と100円が50枚で3010円、つるかめ算で枚数を出しにいく。
10×50=500円
3010-500=2510円
2510÷(100-10)=✖ ・・・ 不適
・500円玉=5枚、10円玉=2枚のとき
合計金額は500×5+10×2=2520円
10円と100円が50枚で2520円、つるかめ算で枚数を出しにいく。
10×50=500円
2520-500=2020円
2020÷(100-10)=✖ ・・・ 不適
・500円玉=4枚、10円玉=3枚のとき
合計金額は500×4+10×3=2030円
10円と100円が50枚で2030円、つるかめ算で枚数を出しにいく。
10×50=500円
2030-500=1530円
1530÷(100-10)=17枚
⇒ 100円玉=17枚、10円玉=50-17=33枚
同じように、500円玉=3枚、2枚、1枚、0枚、を計算するとどれも不適になる。
まとめてみる。
10円玉33枚と100円玉17枚で50枚2030円
⇒ 500円玉4枚と10円玉3枚で7枚2030円
よって、答えは17枚となる。
にほんブログ村