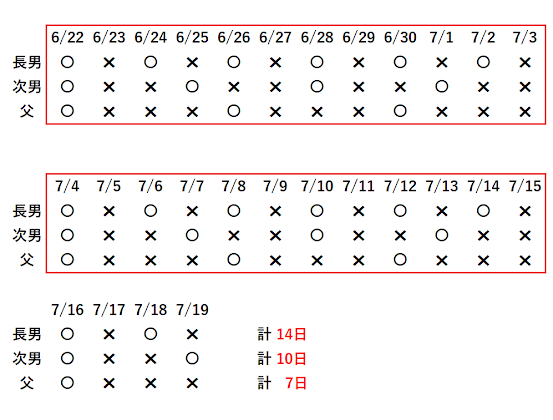【 問題 】3~4年生向け
大きな水そうには3つの排水口A、B、Cが付いています。Aを4分、Bを20分、Cを9分だけ開けると満水の水そうは空になり、Aを5分、Bを4分、Cを3分だけ開けると満水の水そうは半分の水の量になります。また、AとCの2つを開けると、満水の水そうは10分で空になります。AとBの2つを開けると、満水の水そうは何分何秒で空になりますか。
【 解答 】
ただの消去算だね。丁寧に立式して丁寧に解きにかかろう。
では、いきます。
A×4分+B×20分+C×9分=満水の量
A×5分+B×4分+C×3分=満水の半分の量
A×10分+C×10分=満水の量
この3つの式はいいね。文章どおりに式を作った。
満水の半分の量の式を×2して満水の量にそろえようか。
A×4分+B×20分+C×9分=満水の量
A×10分+B×8分+C×6分=満水の量
A×10分+C×10分=満水の量
A×10分が同じだから、2つ目と3つ目の式を解いてあげる。
A×10分+B×8分+C×6分=A×10分+C×10分
⇒ B×8分+C×6分=C×10分
⇒ B×8分=C×4分
⇒ B:C=4:8=1:2(逆比だね!)
ここで次のようにおく。
Bが1分間で排水する水の量=①
Cが1分間で排水する水の量=②
これを満水の量でそろえた1つ目と2つ目の式に入れてあげる。
A×4分+①×20分+②×9分=満水の量
A×10分+①×8分+②×6分=満水の量
⇒ A×4分+①×20分+②×9分=A×10分+①×8分+②×6分
⇒ A×4分+⑳+⑱=A×10分+⑧+⑫
⇒ A×4分+㊳=A×10分+⑳
⇒ A×6分=⑱
⇒ A=③
そう、Aが1分間で排水する水の量=③なんだ。
できました☆
A×4分+B×20分+C×9分=満水の量
⇒ ③×4分+①×20分+②×9分=満水の量
⇒ ⑫+⑳+⑱=㊿=満水の量
この満水の量=㊿を、A=③とB=①で排水するんだ。
(③+①)×▢分=㊿
⇒ ④×▢=㊿
⇒ ▢=12.5
⇒ 12.5分=12分30秒
AとBの2つを開けると12分30秒で満水の水そうが空になるんだね。
よって、答えは12分30秒となる。
にほんブログ村