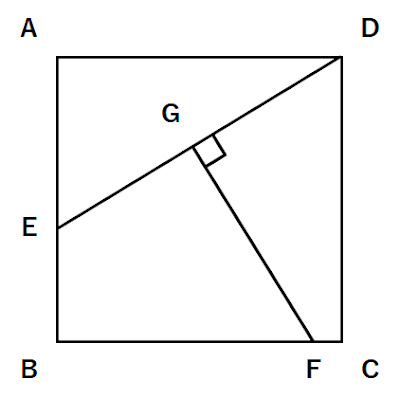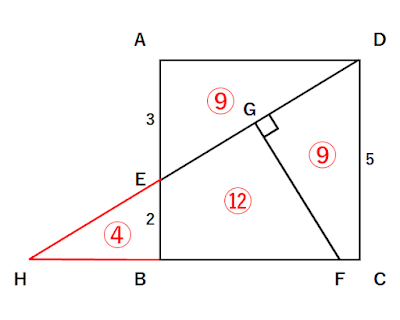【 問題 】4年生向け
3%の食塩水450gと5%の食塩水90gと食塩▢gを混ぜたら10%の食塩水ができました。
▢にあてはまる数字はいくつですか。
【 解答 】
食塩水の基本問題。これをどう解くか。
1つは、天秤図。
食塩のやり取りを天秤図、でやってあげる。
もう1つは、食塩/食塩水。
差が変わらないから差をそろえる=倍数算、でやってあげる。
この問題であれば、生徒の習熟度次第ではあるけど、僕は天秤図を優先で教える。でも、食塩/食塩水も教えると思う。両方とも大事だから、両方を提示する。別の解き方を生徒がしてくれるなら、それは生かしながら進める。
何が言いたいかというと、算数は教え手・解き手によって解き方が大きく異なる。解き方が異なるのは構わない、ただ、とくに教え手について言えることなんだけど、一貫性と再現性だけは気にしないといけない。
では、いきましょう。
まずは、天秤図から。
10%を基準にして、右側の濃い食塩水から、左側の薄い食塩水に食塩をあげてるんだ。
そう、あげる食塩の量ともらう食塩の量がつり合ってるんだ。
右側のあげる食塩:▢g×(100-10)%
左側のもらう食塩:450g×(10-3)%+90g×(10-5)%
右側の食塩水は食塩をあげて10%に、左側の食塩水は食塩をもらって10%になるんだ。
これを理科のてこの原理みたいに書くと上のような感じになる。
▢×(100-10)=450×(10-3)+90×(10-5)
⇒ ▢×90=3600
⇒ ▢=40
食塩水が4種類でも5種類でもいけるから便利だとは思う。
次は、食塩/食塩水で解いてみる。
全部の食塩水と食塩を足したら濃度が10%=1/10になった。
分母に食塩水、分子に食塩を書いてあげる。
食塩▢gの▢は分子と分母の両方に書くんだよ、だって、食塩水=食塩+水、でしょ。食塩を加えれば、当然、食塩水の量も増える。
あとは、差が変わらない倍数算。
同じ▢を足したのだから分母と分子の差は変わらないはず、だから、そろえてあげる。
分母と分子の差
540-18=522g
この差の522gは変わらない。
1/10の分母と分子の差
10-1=9
⇒ 522÷9=58倍
⇒ 1/10=58/580
そう、1/10というのは約分する前は、58g/580g、だったんだね。
18+▢=58
540+▢=580
⇒ ▢=40
小学生は天秤図を書くの巧いし速いからね、天秤図で感覚を鍛えた方が良いかも。
よって、答えは40となる。
 にほんブログ村
にほんブログ村